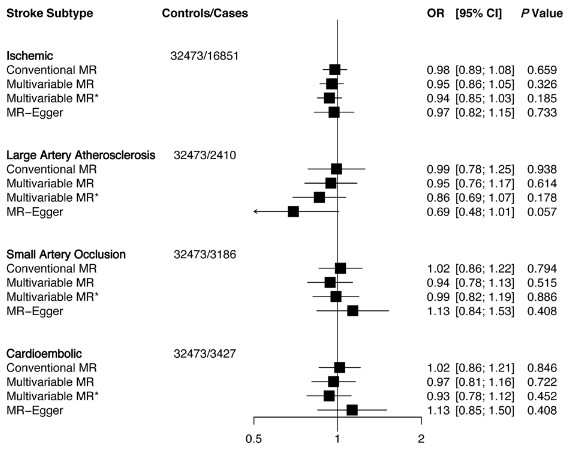元
How central is central post-stroke pain? The role of afferent input in post-stroke neuropathic pain: a prospective open-label pilot study.
2018 3月 アメリカ
脳卒中患者の39-55%は頭痛や肩の痛み、痙縮、中枢性疼痛などのなんらかの痛みを経験する。
しかしこれら痛みケースの4分の1を占める中枢性疼痛のメカニズムはよくわかっていない。
中枢性疼痛は損傷脳と反対側におき、特に上肢や下肢で痛むことがおおい。
通常 慢性的な痛みで、感覚過敏、痛覚や温覚の異常を伴うこともおおく有効な治療法がない。
これまで 中枢神経にある痛みを受容する部分とくに視床のニューロンが脳損傷により過活動になり抑制が効かなくなってしまうことが痛みの原因であると考えられてきた。
今回、中枢性疼痛の原因が「末梢から中枢へ向かう神経シグナルが中枢で誤解釈されるため」という仮説を立てた。そこで途中の神経をブロックすることでこの痛みが消えるものか検証してみたそうな。
脳卒中で中枢性疼痛のある8人の患者について、
疼痛のある部位から中枢へ向かう神経の正確な途上位置に局所麻酔薬リドカインを打ち神経をブロックした。
次のようになった。
・8人中7人で30分以内に痛みが完全に消失した。残りの1人も痛みが50%以上緩和した。
・このとき痛みスケールの中央値は 6.5→0に下がった。
・他の感覚異常も神経ブロックにより消えた。
中枢性疼痛は中枢神経システムの中で自律的に発生するというよりも、末梢からの求心性の感覚刺激に依存し おそらくはその誤解釈によるものと考えられる、
というおはなし。

感想:
比較対照群のない実験だけど、この説は支持したい。
でも誤解釈は痛みについてだけなんだろうか? じぶんの世界認識も誤ってはいないだろうか、、、って心配になるよ。