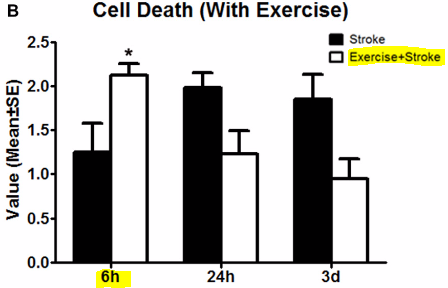元
Prefrontal cortex activation during a dual task in patients with stroke.
2017 10月 日本
身体運動と認知活動を同時におこなう二重課題では いずれかもしくは両方の課題パフォーマンスが低下する。
脳卒中患者ではこれが転倒の原因になりうる。
二重課題には前頭前皮質がつよく関係していることが報告されているので、脳卒中患者について二重課題中の前頭前皮質の活動と各課題パフォーマンスとの関連についてしらべてみたそうな。
脳卒中患者14人と健常者14人について、二重課題時の前頭前皮質の活動をマルチチャンネルの近赤外線センサーを装着しながら測定した。
歩行課題と連続引き算課題を単一もしくは二重で与えたときの 歩行加速度と引き算精度から各パフォーマンス変化を評価した。
次のようになった。
・二重課題時のパフォーマンス低下度はいずれの課題も脳卒中患者であきらかにおおきかった。
・二重課題時の前頭前皮質の活動も脳卒中患者が弱かった。
・右の前頭前皮質の活動が脳卒中患者の身体活動パフォーマンスに関連するいっぽう、
・左の前頭前皮質は健常者の認知機能パフォーマンスに関連していた。
二重課題時に前頭前皮質が優先する課題の種類は脳卒中患者と健常者で異なっていた、
というおはなし。

感想:
運転しながら音楽聴いたり会話する余裕がでてきたよ さいきん。
二重課題で歩行能力アップ
歩きながら考え事すると脳はどうなるの?