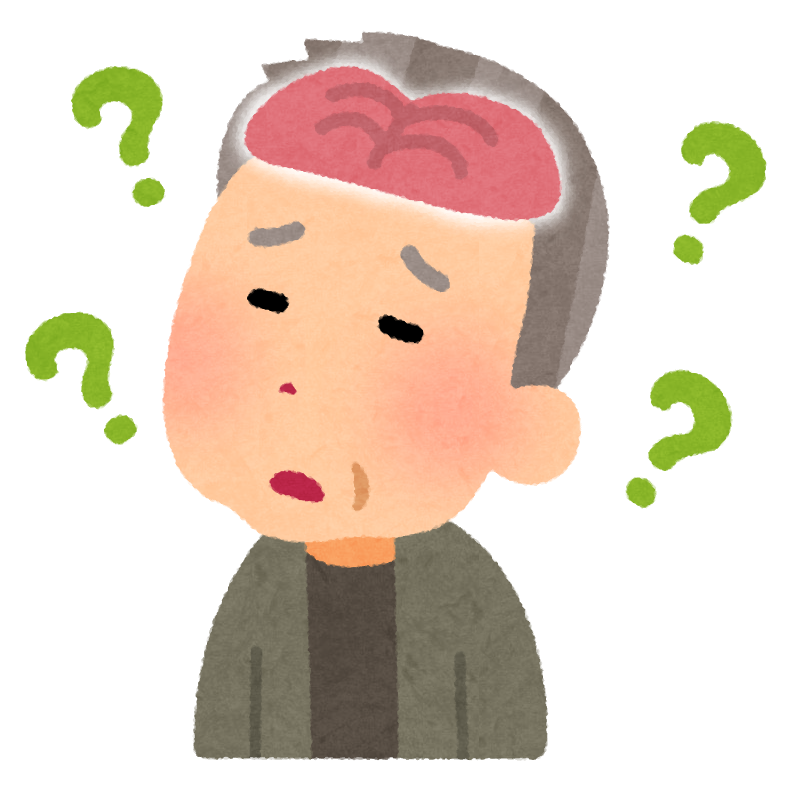元
Association of single and multiple aneurysms with tobacco abuse- an @neurIST risk analysis
2019 7月 スイス
未破裂脳動脈瘤は成人の3.2%にあるとされ、画像診断技術の進歩により発見されるケースは増加傾向にある。
これら未破裂脳動脈瘤をすぐに治療するべきか経過観察するべきかはおおくの要因にかかっている。その1つは喫煙と考えられる。
これまでの研究のメタアナリシスでは、喫煙習慣は 改善可能なもっともおおきなくも膜下出血のリスク要因であることを示唆している。
しかし最近では喫煙と脳動脈瘤の破裂との関連を示さない報告がいくつかでてきた。
そこで、スイスの未破裂脳動脈瘤のデータベース @neurIST をもちいて喫煙と脳動脈瘤の形成そして破裂(くも膜下出血) との関連を大規模にしらべてみたそうな。
次のことがわかった。
・未破裂脳動脈瘤の1410人を一般人30万人とくらべたとき、喫煙者率は脳動脈瘤患者で高かった。(56.2% vs. 51.4%)
・喫煙は脳動脈瘤の存在とあきらかに関連し、多発性脳動脈瘤とも関連していた。
・喫煙の期間と多発性脳動脈瘤リスクとに関連がみられた。
・しかしくも膜下出血をおこした(破裂)患者での喫煙者率は未破裂患者のそれと同じだった。
喫煙は脳動脈瘤の形成に関連していた。しかし喫煙で脳動脈瘤の破裂リスクが上がるわけではなかった。喫煙期間が長いと多発性脳動脈瘤になりやすかった、
といういおはなし。

感想:
MRIが普及して未破裂脳動脈瘤をフォローできるようになったからこその知見だな。