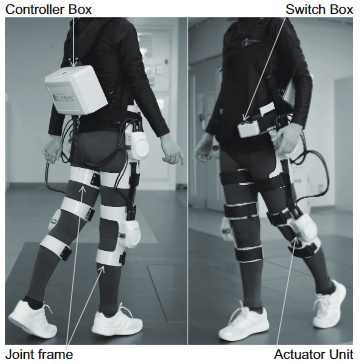元2025 10月 イギリス
脳卒中のあと、どのくらい機能が回復するかには個人差があり、一般的には年齢や発症時の重症度、発症前の生活レベルなどが、その予測に使われている。
でも実は、「性格」も回復の具合に関係しているのではないか、という考え方がある。
性格というのは、ある人の考え方や感じ方、行動の傾向のことを指す。なかでも、ビッグファイブと呼ばれる有名な性格モデルでは、神経症傾向、外向性、開放性、協調性、誠実性の5つの特性がある。
これまでの研究では、たとえば神経症傾向が強い人は脳卒中後にうつや疲れを感じやすいことが分かっている。でも、こういった性格の違いが、日常生活の回復などに直接どれくらい影響するのかは、まだよくわかっていない。
そこで、「性格」と「脳卒中後の機能的な回復」との関係を調べた過去の論文を集めて、全体としてどんな傾向があるかをくわしくしらべてみたそうな。